日本ホスピス在宅ケア研究会in久留米にて講演させていただいた際の内容の文字起こしです。
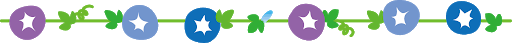
西栄寺 介護福祉事業部の吉田敬一と申します。
東北大学大学院 文学研究科 実践宗教学寄附講座・臨床宗教師研修の記念すべき第一期生として、臨床宗教師の実践と事例と題した現場リポートをお話しさせていただきます。
現在、西栄寺内に介護福祉部を新設して、「お寺の介護はいにこぽん」という事業名称で、訪問介護・居宅介護支援・障がい福祉・通所介護・高齢者住宅サ高住を運営しています。私にとっては、臨床宗教師の実践といえば、お寺が主体となった介護事業の実践となります。
現在は 東北大学の臨床宗教師研修と種智院大学の臨床宗教師研修の現場実習を一部我々の介護福祉部が受け持っております。
「お坊さんヘルパー」というジャンルを確立すべく、特に訪問介護の現場で奮闘しています。さらに地域の病院や福祉施設地域包括支援センターの依頼で、問題を抱えている支援の必要な方のもとに伺い、じっくりとお話を聞いて、次の段階の支援につなげていくような試みも行なっています。
私にとって、お坊さんヘルパーと臨床宗教師は地脈でつながっています。
最初は僧侶として、なにか行動を起こしたいという一心からホームヘルパーを取得し高齢者施設にボランティアとして伺いました。その活動名が「聞き屋」といいます。
お坊さんとお話しませんか?をキャッチコピーにした傾聴ボランティアです。
でも実際は、話を聞くだけではなくそのほかなんでもします。入浴介助、食事介助、トイレ介助、お使い、お部屋掃除。つまり、ご用聞き屋です。
東北大学で臨床宗教師研修を受講した後、市内の緩和ケアホスピスでも活動をしました。
どういうことをするかというと、朝の看護師さんの申し送りに参加し、その後、環境整備の一環で、すべての患者さんのお部屋に伺ってお声をお掛けします。
そうして、お話が進みそうな様子の方は、後に看護師長さんの承諾を得て再度病室に訪問します。その他、買い物の付き添いや、散歩に同行しながらお話をお聞きします。特に散歩を機に患者さまと打ち解けることが多くあります。患者さんが何らかの処置中にご家族が談話室などで時間を持て余していたらさりげなくお声をかけて世間話などをします。
ある日、談話室でたたずむ男性に声を掛けました。その男性の奥さまが入院されていて、すでに奥さまはコミュニケーションがとりにくい状態です。お二人の間には子供が居ません。男性は毎日一人で奥様に会いに来ていました。
男性と何度か雑談をするうちに「奥さんにどう接したらいいかわからない」という男性の悩みを聞きました。
奥さまが、その男性、つまりご主人のことが認知できなくなっている、というさみしさや、話ができるうちに感謝の気持ちを伝えたかった、というお話をお聞きしました。
私は男性に、奥さまに対して 「大丈夫やで」「安心しいや」「ありがとうな」と簡単な言葉で なんどもなんども声をかけてみてはいかがですかとお伝えしました。
すると、それまでは大声を出したりなったりすることが多い奥さまが、ご主人の声を聞くたびに落ち着くようになり、ご主人自身にも笑顔が見られるようになりました。
院内でも介護の現場でも基本は徹底的に聴き役です。患者さん利用者さんに話をするように誘導したりせず、また、話が出ないことでこちらが焦らないように注意して、患者さん利用者さんが話したいと思うまではひたすらに待ちます。
特に院内では、患者さんの病状やコンディションによっては、その日の結果、誰ともお話しすることなく一日終わることもありますが、そういう日は、談話室や台所の掃除をひたすらにするなど、できることはなんでもしています。
患者さんはもとより、ドクターや看護師さんから依頼があれば断らずなんでもお手伝いします。
聞き屋だからといって、いきなり話を聞きますと現れてもほとんどの人が話そうとされません。したがって聞き屋は、さまざまな雑用の依頼を受けることからはじまります。そして、用事を言いつけてもらうためにこころがけていることがあります。
それは「ちょうどええとこに来たな!」と言ってもらえるようなところを探す。これは患者さんから与えていただいた私の課題です。
ある男性の病室に昼食後の食器を下げにお邪魔したら「ちょうどええとこに来たな」「タバコ吸いにつれて出てくれへんか」と言われました。看護師さんに相談しましたら「見て見ぬ振りするから….」と。患者さんは「助かるわあ」とよろこんで、「毎回、昼食後に来てくれへんか」とも言われ、それ以後この男性のたばこ外出に幾度となく付き添い、その男性の話が深まっていきました。
離婚した話。子供から嫌われている話。仕事の自慢話。母親の話に至った時は声を出して涙を流されました。
男性は現役世代です。自身に起きたことに対する思いを、絞り出すような声で「くやしい」と言われました。
「死んだらどうなるか」と聞かれ、「先に亡くなったお母様と再会して抱きしめてもらってください」と伝えしました。
私の場合、お話をお聞きするときの姿勢は、できるだけ横並びに位置して向き合わないようにします。話が深まれば、その話を聴く姿勢を保つだけで汗がしたたり落ちることもあります。それだけ聞くという行為は力を使うと思います。でもこれらは技ではないと思います。技法的に学ぶのではなく、人格に依るところの総合力が支えると、私は考えています。その人格形成に宗教はとても重要かと思います。
介護事業でも病棟での活動でも季節の行事があるときは、積極的に参加します。これは 初めて緩和ケア病棟の夏祭りに参加した時、たこ焼き、カキ氷、わたがしの屋台をお手伝いしたのですが、患者さんが活き活きしている姿に感動しました。普段はなかなか食事がのどを通らないと言われている患者さんも、ノンアルコールビールで乾杯し、たこ焼きをお代わりして、そのことで看護師さんを驚かせたりしていて。ここで、お祭りという行事の力を知りました。
クリスマスには、患者さんのリクエストでサンタクロースに扮しましたが、このときは 看護師さんたちに「サンタク、、、ボーズ!」といわれてかなり好評を博しました。
ある六十代の女性は、私の母と同じ年齢。お刺身が好きで、病院の隣のスーパーにお刺身を一緒に買いに行きましたが、「量が多いので小分けして欲しい」と店員さんに交渉をはじめました。スーパーのパックになっているお刺身を小分けしなおすのは難しいのではと私は内心心配になりましたが、交渉に交渉を重ね、さらに自分の余命がそう長くないことを武器にして刺身の小分けを勝ち取った。とても満足そうでした。私が「やりましたね」というと、「これが主婦の楽しみや」と言われました。
ここで感じたのは、終末期といっても患者さんは今まで通りの日常を過ごすことがとても大切で、楽しみにしていることなどを行うことが終末期でも支えになるということ。「それでも楽しみたい」 「日常にこそ楽しみがある」それができるようにお手伝いをするんですね。このお刺身の女性は、心の想いを深く語ることはありませんでした。でも 、主婦として三人の子供の育てるために日々スーパーに通って子供たちのためにおいしい食事を作ってきた。そんな誇り高き母の姿をその時点で私は聞かされていたことになる。これもひとつの聞く形。「日々スーパーに行っておいしいご飯を作って子供たちに欠かさず食べさせてきたんですね。本当にお疲れさまです。」「いやいや、いつもあるもんでちゃちゃと作るだけや。」と言いつつ 涙を浮かべられた姿は強く印象に残っています。
終末期では、その人の死への恐怖や苦悩の話を聞いてそれを慰める。もちろんそれは大切なこと。しかし、そうはいっても、自分の苦しい気持ちを言葉にすることはとても難しいことです。そもそも言葉にできるほど単純な気持ちではないのです。だから話そうとする人は実は少ない。むしろ話せない、というべきかもしれません。
したがって、終末期では、誰にも自分の気持ちを話すことなく一人きりで自分の命と向き合う人が多いように感じます。
そして、多くの人は、死に直面した時の恐怖に一人で向き合う強さを持っている。
でも、その強さがくずれる瞬間があります。
ある病室にお茶の交換に伺いました。その病室の男性から、「テレビの上にあるティッシュを取ってほしい」と言われました。
私は男性の手の届くところに置いて差し上げました。すると、急に私の手を強く握られました。私も両手で強く握り返した。その男性は、咳が激しく常にタンが出るんですね。手の届くところにティッシュが必要なんです。でも看護師さんが 処置のあと忘れたんですね。何気ないことなんですが、その男性は私に言いました。「誰もわかってない 何がホスピスや!」と。そして「たすけてくれ」と嗚咽しました。
私は「心残りなことがすべて消え如来の大悲に抱かれますよう」と、なんども小声で祈りました。
終末期医療や介護の現場の中にお坊さんがいることは不謹慎という考えもあります。その考えには十分配慮をしつつ、宗教者という鎧をつけないようにこころがけ、まずは宗教者已然の私自身がこの場でどうあるべきかを意識しています。
患者さんが、医者でも看護師でも宗教者でもない私自身を身近で損得のないただの近所のおっさんとして受け止めてくださった方が自然と対話が生まれるだろうし、そのうえで、話してよかったと、お聞きしてよかったとお互いが感じれるようにすることを目標にしています。そして、宗教的なことばやしぐさなどはほとんど出さずに、ただし、雰囲気は感じていただくように意識し、そのことを持って、その方のやすらぎにつながることを最大限の目標にしています。
これはつまり、臨床宗教師、僧侶、お坊さんヘルパー、おせっかいな近所のボランティア。どの私が支援者なのかを評価するのは患者さんや利用者さん側で、私が行う支援が 宗教的特性を活かした支援かどうかを 評価するのも患者さんや利用者さん側だということを現場で学んだからこその考え方です。
今現在は、当寺の介護福祉事業部で「お寺の介護はいにこぽん」の責任者を務めて専念しております。この、はい、にこ、ぽんですが、はい即答、にこっと笑顔、ポンと実行という教訓です。
開設二年半を迎えますが、利用者は100名ほどに至っております。僭越ながら介護事業としては優秀な成績だそうです。
これは、お寺の介護やお坊さんヘルパーといった目新しさの中にも、お寺やお坊さんという存在が、古くから培われてきた信頼がまだまだ活かされていると自己評価しています。
ここで、お坊さんヘルパーの特徴と役割について解説申し上げたいと思います。
お坊さんヘルパーは、一次的には普通の男性ホームヘルパーとしての介助に徹し、二次的に、高齢者の信仰に基づいたお話の傾聴、家族との死別による悲嘆へのグリーフケア、また宗教的道具などへの丁寧なアプローチをするなどの宗教的ケアで、高齢者の心の自立支援を補助するのが役割です。これら一次的二次的な支援を場面に応じて連続的かつ重層的に実践することがお坊さんヘルパーの最大の特徴であります。、
さらに、われわれの介護福祉事業部には、お坊さんヘルパーと共に普通のホームヘルパーも在籍しており、それぞれが高齢者の要望に添った支援をしていますが、普通のホームヘルパーが抱える体力的また精神的負担を緩和するためにお坊さんヘルパーが後方支援することも欠かさないようにしています。
宗教者は、教義の伝道によって信者の教化を図ることが本分ですが、お坊さんヘルパーは、お坊さんヘルパーでいる時は教義で導くことはあえて行わないようにしています。そのようなことをあえてしなくても、むしろ、伝道を行わない時や行うべきではない時にこそ新たな宗教者の姿があるのではないだろうかと模索して生まれたのが、お坊さんヘルパーということです。宗教を語らない宗教者という存在。でも宗教が人を支えることは間違いない。これはまさに、臨床宗教師の研修で得た学びがそのまま活かされているというわけです。
在宅支援、訪問介護というフィールド、日常というシチュエーションにおける支援で最も重視しなければならないのは、被支援者本位と自立支援です。身体的支援であれ、生活援助であれ、また教義の伝道であれ、過剰な支援は支援の依存を生んでしまい、逆にその方の生活の質を低下させてしまう恐れがあります。そこを踏まえて適正な支援を計画することは極めて重要です。
ここでは専門家としての考え方や援助の技術、また多職種連携のスキルが必要であり、宗教者が福祉支援の現場に出る際に最大限に自戒しなければならないところです。
ある利用者は身寄りがありません。そして末期のガンです。
最期は長年住んだご本人の自宅に帰って過ごしたいとの希望で、入院先の病院から退院の手配を我々が準備しました。ドクターとも打ち合わせを重ねて、医療的なケアは訪問看護を手配して、お坊さんヘルパーや女性ヘルパーが入れ替わりに訪問するような介護計画を立てました。
そしていよいよ我が家に戻られました。翌日、ケアマネが朝一番で様子の確認に伺いましたが夕べのうちにお亡くなりになっていたんですね。
われわれはとてもショックを受けました。ご本人の希望とはいえ本当によかったのかどうか。ご自分の家とはいえたった1日過ごしただけで、そして、たった一人で旅立たせたことが良かったといえるのかと。
この件については介護部みんなで話し合いました。かなり真剣に話し合った結果、退院してきた日の嬉しそうなお顔や、私たちに何度も「ありがとう」ってお礼を言ってくださったこと、またその方の最後はただ一人だったとしても、それはその方が暮らしてきた家にある空気や思い出の詰まった生活用品に包まれた一夜であり、その方の日常という幸せを噛みしめたひと時だったに違いないという結論に至りました。
けれども、ほんとうによかったのかどうか…この意味を考えながらこれからも進んで行かなくてはならないと気持ちを強くしています。
あらためて臨床宗教師とは、医療や介護福祉など現場に赴き、宗教者の特性を活かした対人援助を行うため一定のスキルを学ぶための研修を受講するところから始まります。研修後は、それぞれが自らの行える範囲で自分らしい対人援助を日常の中で模索しながら活動していく。さらに、ひとたび震災などが発生すれば臨床宗教師仲間の連携によって的確な被災地支援を実施する。ということになろうかと考えています。
臨床宗教師がどれだけ臨床という現場で活躍できるかというと、それは先ほども言いましたが、臨床宗教師、、僧侶、お坊さんヘルパー、おせっかいな近所のボランティア、どの私が支援者なのかを評価するのは患者さんや利用者さん側で、私が行う支援が 宗教的特性を活かした支援かどうかを評価するのも患者さんや利用者さん側なんだということをふまえて立場や知識などが削ぎ落とされたただのおっさんの私が苦悩や悲嘆の渦中で、患者さんや利用者さん檀信徒と共にもがきながら一筋の光を見出していく、これが宗教の原点であろうし、これこそが臨床宗教師の実践であると、こう考えています。
