南無阿弥陀仏をとなえれば
十方無量の諸仏は
百重千重囲繞して
喜びまもりたもうなり…和讃
阿弥陀とは、“計り知れない永遠の”と捉えて仏は“命”と見ます。
阿弥陀さまとは、これつまり“永遠の命”と解釈します。
永遠の命とは、命のつながりのことで、私たちの命は遥か昔から脈々と繋がってきた命であります。
地球が誕生し海ができ、微生物が生まれてから現在に至るまで、生きとし生けるもの全ての命は果たしてどれくらいあったでしょうか。
決して数えることはできない無数の命、この総称が“阿弥陀仏”と私は考えています。
投稿者: 44da99@gmail.com
テロメア!
最近話題の「命の回数券・テロメア」
テロメアは、人の寿命に大きく関わっているとされ、細胞の中の染色体の先端部分にある物質で、テロメアの不活性が、ガン発生の原因であったり、老化を早めたり、寿命を縮めるということがわかっているそうです。
このテロメアを活性させ健康寿命を伸ばす方法が盛んに研究されていますが、最近判明しつつあるテロメア活性方法のひとつに「瞑想」が効果抜群だそうです。
「瞑想」とは呼吸を一定に整え、心と頭の中を静寂に保つための行ですが、これはお釈迦さまが長年の修行で会得した悟りを開く方法です。
お釈迦さまは80歳まで生きられましたが、当時の80歳は超長生きと言っても過言ではありません。これはきっと瞑想によって、お釈迦さまのテロメアが活性化されていたと考えても良いのではないでしょうか。
これで、仏教は優れた健康法だということが証明されたわけですね。
まあ、私の場合は、知る人ぞ知る“迷走”の達人として崇められて!?いますので、ことさら動じることも御座いません。
(-ノ-)/Ωチーン
葬送儀礼所感その4
人間は死後、生まれ変わることができるのでしょうか。
大切な人を亡くした遺族の心情から察すると、亡くなった人はもう一度この世に生まれ変わってきて欲しいと願うものです。
例えば、故人のことに想い忍んでいると、窓際に雀が飛んできて、怖がりもせずじっとしてる様子などを見たとき「これは故人の生まれ変わりかもしれない」と感じるものです。
生まれ変わりが有るのか無いのかを知性で理解しようとしても、答えは出ません。
それよりも、亡くなった方の存在を身近に感じれるよう自身の感受性を高めていくことが、供養のひとついえるのではないでしょうか。
葬送儀礼所感その3
古代日本人より抱き続けている、この世界とは別の世界が存在するという「他界観念」。
それを〝天〟と呼び、また、〝極楽〟とも呼んで、いずれも人の死を界に到達すると信じられている。
宗教学では、この世と連続の認められる他界を「連続的他界観念」とし、この世とは連続せず、全く別次元で存在すると考えられる「断絶的他界観念」と、二つの観念が位置付けられれている。
仏教でもっとも語られる他界は、一切の苦悩から解き放たれ極めて安らかな場所「極楽浄土」である。

葬送儀礼所感その2
葬送儀礼において、お経を唱えるというのは供養の一つといえます。
お経とは、お釈迦さまが語られた言葉を後々物語調に記したもので、その数は八万四千ともいわれています。
浄土真宗では、「浄土三部経」が根本聖典として、お釈迦さまの「出世本懐」の教えを聞かせていただくのが、お経を唱えることの意味です。
さらには、お釈迦さまの本意を明らかにされた七高僧や親鸞聖人ご教導の「偈文」をお経とともに唱え、その意味は、阿弥陀仏が願われた『あらゆる時代の全ての人々、命ある全ての生きものが等しく御救い導かれる』ことを聞かせていただき得心することが、お経を拝読することの重要な意味であります。
比較政治学
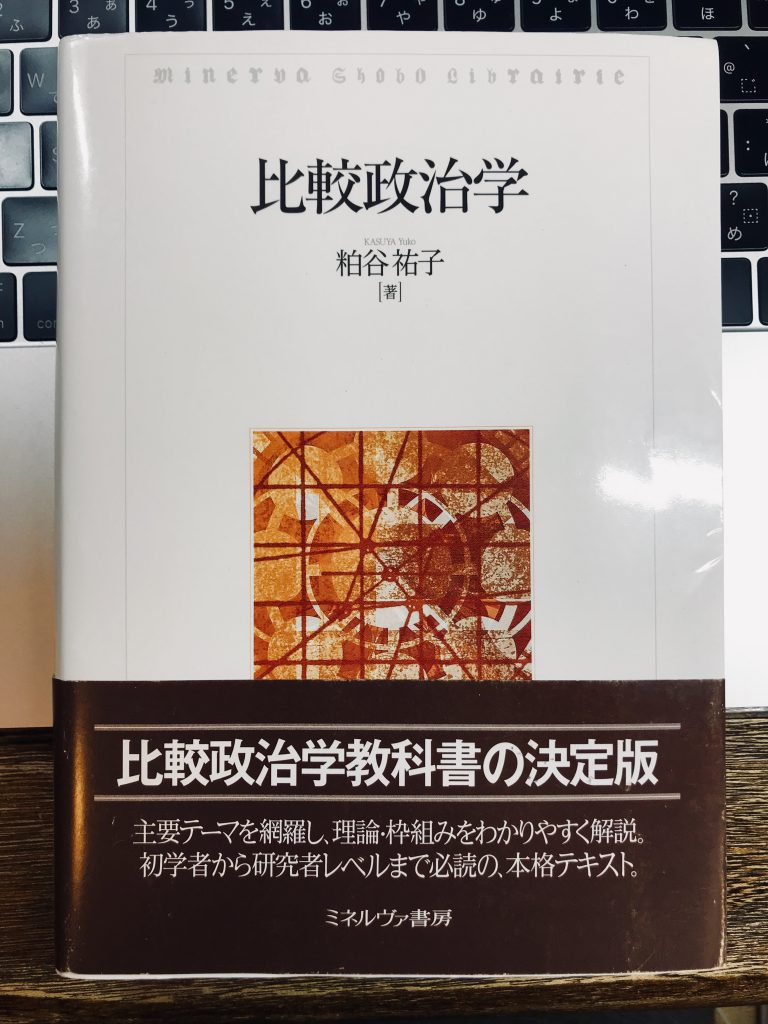
レポートの設題
日本・アメリカ・中国、各国のトップに位置する政治指導者の選出方法の特徴を政治体制の異同も含めて比較考察せよ。
政治という現象を理論的に分析し、さらに世界各国の政治を比較研究する学問が比較政治学です。
国家建設/市民社会/ナショナリズム/内戦/政治体制としての民主主義
民主化/民主主義体制と政治文化/権威主義体制の持続/選挙制度
政党と政治システム/執行府・議会関係/福祉国家
予防介護運動指導員
今後、高齢者に対する福祉は予防介護が主流になります。
介護が必要とならないように日頃の運動が極めて重要になります。
でも闇雲に身体を動かしても効果は得られません。
とはいえ、難しく考える必要もありません。
普段の暮らしに少し工夫をすれば、効果の高い運動が可能になります。
お坊さんヘルパーも予防介護に力を入れて利用者さんの暮らしを支えていきます。
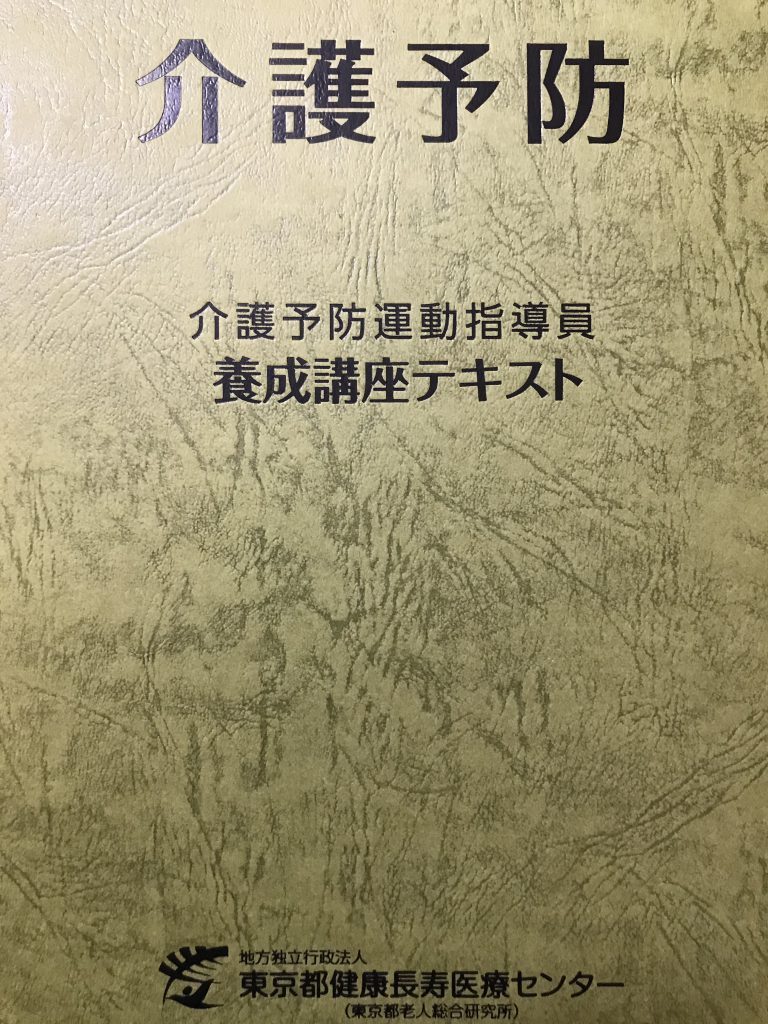
葬送儀礼所感その1
死とはどのようなことをいうのだろうか。
もちろん、生命学、医学、倫理的に、
さらには法律によって死は定義されていることは承知している。
もし、身体が生命体の全てだとしたら、身体の機能が停止した段階、そして、例えば火葬された時点で、私たちが通常考える死が訪れたといえる。
それでは、心や思考や体験はどうなるのか。
一人の生命体がこの世に生まれた事実は、死が訪れても急に消え去ったりしない。つまり死というのは、私たち身近な者の前に五感に感じる範囲で居なくなることに過ぎない。大局で死を捉え、死に対する問いを深め、死を受容していく過程が宗教である。
新年の挨拶
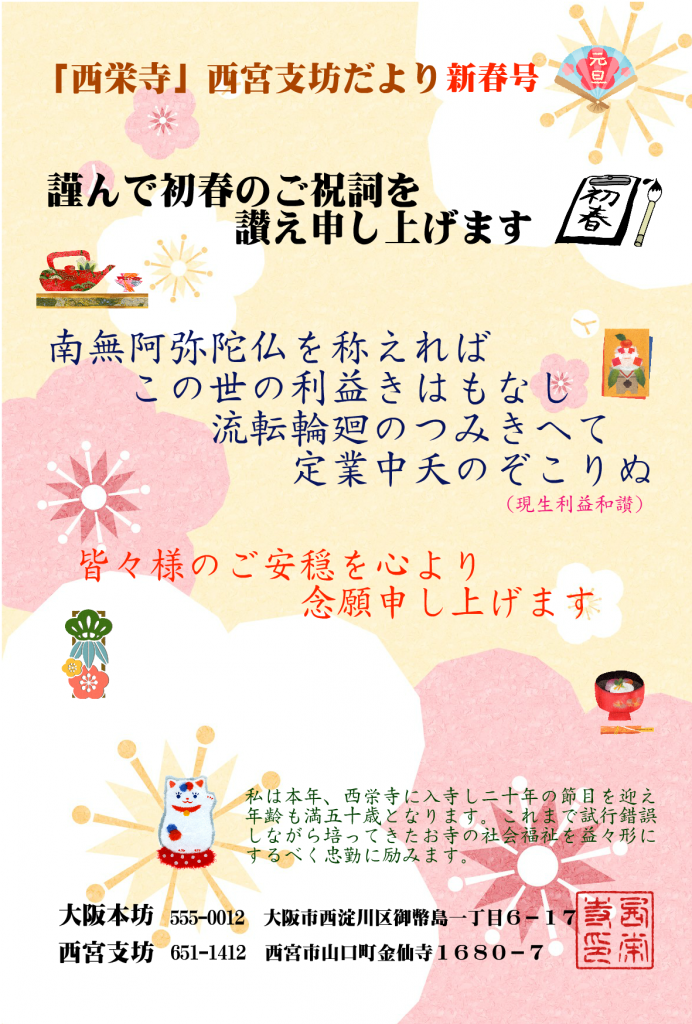
あけましておめでとう御座います!
本年も皆様と共に法縁に恵まれつつ、穏やかな一年となりますよう心より念願を致したく存じます。
年賀状にありますように、本年私は満50歳になり、西栄寺に入寺20年の節目を迎えます。
何事にも感謝の気持ちを忘れずに、少しでも皆様のお役に立てるよう精進を尽くしたいと心を強くしている次第で御座います。
本年も、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
クリスマス!
お寺の介護はいにこぽんデイサービスのクリスマス会です。
お寺でクリスマス!?
今更ながら、クリスマスはキリスト教の宗教儀式ではありますが、世界中どこでも宗教を越えた季節の行事となりました。
当事業所では、お釈迦さまもサンタに扮していただき利用者さまとともに楽しんでいただきます。
サンタクぼーず!

